ドキュメント・オブ “10000の瞳”プロジェクト
日本の再生や復興という言葉が繰り返されている今、私たちはこれまでと同じ考え方、価値観の継続ではそれを望めないと気づいています。猛スピードで技術革新という名のもとに、目に見えるもの(物質)を追いかけてきた時代は、目に見えない大切なもの(心や絆)をどこかに置き忘れてきてしまいました。世界からの支援や声援を受け、これからの日本という国の在り方、私たちが生きていく術について、有識者の方々に提言して頂きます。
- 過去という未来
「過去」という未来 ?石巻市立稲井小学校を訪ねて思ったこと?
10月から11月の頭にかけて、石巻市立稲井小学校を訪れる機会が二度あった。『今ある気持ち』という楽曲の、全校生徒による合唱練習とレコーディングを見に行くためである。歌手の上田正樹さんと緑の惑星プロジェクトとのコラボレーションで生まれ、『緑の募金』東日本大震災復興事業応援ソングに採用された歌である。そして、ひたむきに歌う生徒たちの姿にすっかりやられ、少しでも元気になってくれればという私たちスタッフの気負いはいつしか鳴りを潜めてしまった。気がつけば、あまりにも純心無垢な彼ら、彼女らに元気を貰ったのは、むしろ私たちの方であった。震災と津波で肉親を失った児童、母校が被災して転校してきた子もいるのに、なぜそんなに純心無垢でいられるのか? そう考えたとき、幼いながらも「自分」というものを持っているからではないかと思った。「自分」を言い換えれば「個性」であり、それを先生方が尊重し、そして雄大な自然に囲まれて伸びのびと育つことで保たれているのではないかと感じた。そう、人は一人ずつ違って当然。多様であってこそ、お互いに支え合えるのだ。
それは自然界に普遍的に通じる法則である。自然界を弱肉強食の世界と考えるのは、都市社会が生まれ、そこに住む人たちが自分たちに照らし合わせて生じた概念ではないか? 都市社会には、特化した、言い換えれば偏狭な価値観がある。そこでは同じ目的のために競争し、勝ち組、負け組が生まれる。そうした観念で見たのが弱肉強食なのだ。
それでは、自然界とはどんなものなのだろう。40億年近い昔に地球上に誕生した生命は進化を重ね、今の自然界がある。私たち人類は自分たちこそ進化の頂点と信じ、バクテリアなど微生物を原始的で不潔なものと切って捨てる。しかし、人類はバクテリアなくして食べものを満足に消化できず、息を吸うだけでは蛋白質の主原料で大気の75%以上を占める窒素を体内に取り込むことができない。窒素はバクテリアが生態系に最初に取り込み、それを植物が吸収して、やっと私たちを含む動物の血となり肉となる。すなわち、あらゆる生物が連携し融通しあい、調和のうえに成り立つ世界が自然界なのである。
人類社会も元々はそういう世界だったはずである。それが経済と産業の発展に伴い、金と物が至上の画一化社会への道を歩みはじめた。それでも19世紀までは、「博物学」という、ものごとを様々な角度から見る総合的な学問分野があった。しかし、20世紀の資本主義と科学技術の急激な進歩によって、専門分野が細分化され、各分野の画一化が進み、社会の多様性が狭まって、今がある。
だから、21世紀のこれからは、その状況を冷静に見つめなおし、博物学的なものの見方への回帰を図るべき時ではないだろうか。
今回、石巻という「ふるさと」に出合い、20世紀に失われたものが色濃く残っているのを感じた。それを「過去」として葬ることなく再認識し、そして、この災害からの復興に多様で複合的な考え方や手法をもって、より良い「ふるさと」の創生を目指すことが大切だとの思いを深めるのであった。
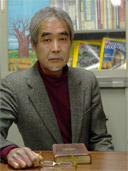 |
吉田 彰
動植物共に固有種が豊富なことで有名な島・マダガスカル。そこで、失われた森の再生活動に取り組んでいる。1973年に初めてマダガスカルを訪れ、その豊かな自然に感動。しかし、その後何度か訪問するたびに森林の荒廃が進むことに心を痛め、1990年にボランティア団体「サザンクロスジャパン協会」の設立に参画。以降20年にわたり植林活動に取り組んできた。その間植えた樹木は11万本を超える。2010年にはその功績から、マダガスカル独立50周年に際して、シュヴァリエ(騎士)Chevalierの称号を受勲。今年1月に放送された「NHKスペシャル 福山雅治ホットスポット 最後の楽園マダガスカル」ではスペシャルアドバイザーを務めている。 |
